Neuro Diveでは、AI(機械学習)やデータ分析(データサイエンス)、業務効率化(RPA)などの先端ITスキルを学び、現場で活かせる実践型のIT人材を育成しています。そのため、受動的な学習だけでなく、課題解決能力を磨くための能動的なアクティブラーニングを実施。実際のビジネス現場に近い開発の流れを体験するポートフォリオ作成や、チーム業務に必要な協働を学べる擬似就労プロジェクトもその一環です。今回は、Neuro Dive渋谷で実施した擬似就労プロジェクトの模様を紹介します。
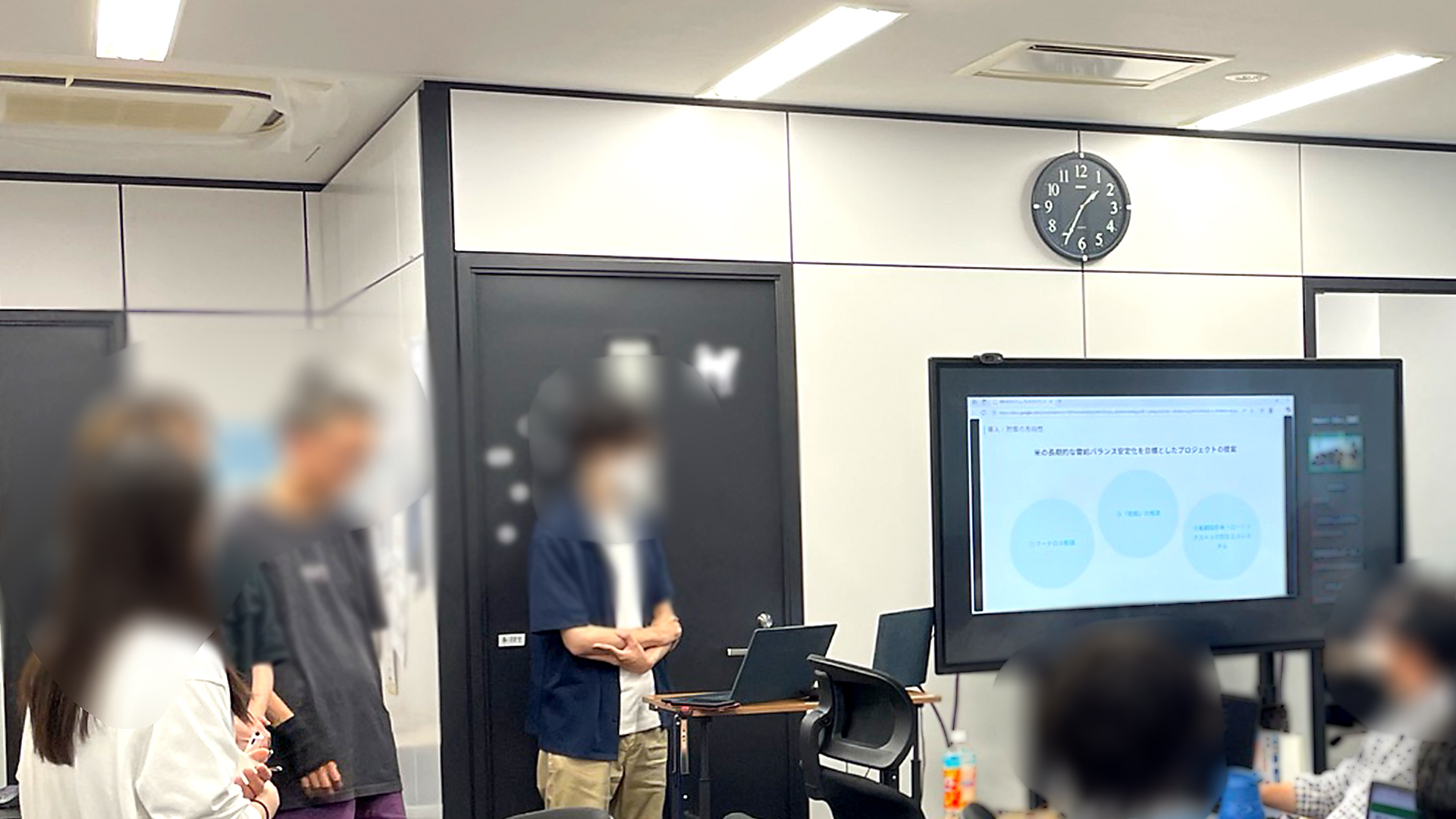
目次
個の力を発揮し、チーム力を最大化
先端IT分野への就労をサポートする就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、即戦力人材の育成を目指して、実際のビジネスシーンを想定したトレーニングを行なっています。その一つである「擬似就労プロジェクト」は、チーム開発が主流となっている先端IT分野で力を発揮できるよう、利用者同士が協働で取り組むチームプロジェクトです。
擬似就労プロジェクトに込めた想い
擬似就労プロジェクトの目的は、主に次の3つです。
- 即戦力人材を目指して、実務に即したITスキルを習得する
- 職業準備性を身につけ、安定的にはたらく土台をつくるビジネスを体感し、就労への不安を軽減する
ITスキルの実践的習得はもちろん、職業準備性(※)のレベルや課題を把握することも、重要な目的の一つです。チームとして成果を挙げるには、「個々のスキルやアサイン状況を可視化する」「不測の事態にも柔軟に対応する」など多面的な能力が求められます。プロジェクトにおけるミスや失敗も、自己成長に向けた貴重な経験となります。
チームプロジェクトの経験は、就職活動時のアピール材料にもなり得ます。「擬似就労プロジェクトで何を担当し、何を得たか」という具体的なエピソードは、自己PRの裏付けとなるでしょう。また、一連の業務フローを経験し「はたらく自信」を養うことは、就労への大きなステップアップとなります。
※「職業準備性」とは:コミュニケーションスキルやスケジュール管理能力など、はたらくための土台となる能力のこと
現役エンジニアのメンターが成長を後押し
擬似就労プロジェクトのメンター(指導者)は、日本最大級のAIコミュニティ「CDLE*¹」の有志グループ(生成モデル)。最前線で活躍する現役エンジニアが、プロフェッショナルな視点でフィードバックを行います。アイスブレイクを活用した雰囲気づくりや、問題解決に向けたフレームワークなど、生きた仕事術を学べる点もポイント。「実際の仕事の進め方」や「課題解決に対しての考え方」をイメージできる絶好の機会です。
*¹CDLE(シードル:Community of Deep Learning Evangelists)とは、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施するG検定およびE資格の合格者が参加する日本最大級のAIコミュニティです。
今回のプログラム内容は「アイデアソン」
毎回、異なる趣向で実施している擬似就労プロジェクトですが、今回は「アイデアソン」を試みました。アイデアソンとは、メンバーがアイデアを出し合い、課題解決のヒントを探るイベントのことです。「2026年の米販売価格を2023年と同水準にするには」というアジェンダを設定し、3チームが農協(JA)職員の視点でアイデアを創出しました。
| プログラム内容:アイデアソン テーマ:「日本での米販売価格」 目標「2026年の米販売価格を2023年と同水準にする」 設定:農協(JA)のスタッフ |
キックオフからプレゼンテーションまで一連の流れを経験
初回オリエンテーションから成果発表会までの期間は2週間。チーム内で各メンバーの能力を把握し役割分担を明確化するところからスタートしました。1週間後、メンターであるCDLE・矢野さんを交え、「ITアドバイザー質問会」を実施。各プロジェクトの内容は実務レベルに達しているか、成功には何が必要かなど、活発な意見が交わされました。
成果発表会における各チームの持ち時間は、発表10分・質疑応答5分の計15分です。スライドやスピーチの構成など、アウトプット方法にも各チームの工夫が感じられました。
表彰制度を導入!シビアな視点で完成度を評価

今回は、フィードバックにとどまらず表彰制度を導入することで、成長機会の充実を図りました。以下のような明確な評価基準を設け、「なぜそのプロジェクトが優れていたか」を事業所内で共有。擬似就労プロジェクト未経験の利用者にとっても、大きな刺激となったようです。
評価基準
| 課程評価 | チームワーク思考力報連相力スケジュール管理力指示理解(役割分担) |
| 成果評価 | リサーチ課題解決・実現可能性プレゼンテーション |
課程評価、成果評価それぞれ採点し、総合力を判定しました。
ユニークなアイデアが飛び出した成果発表会
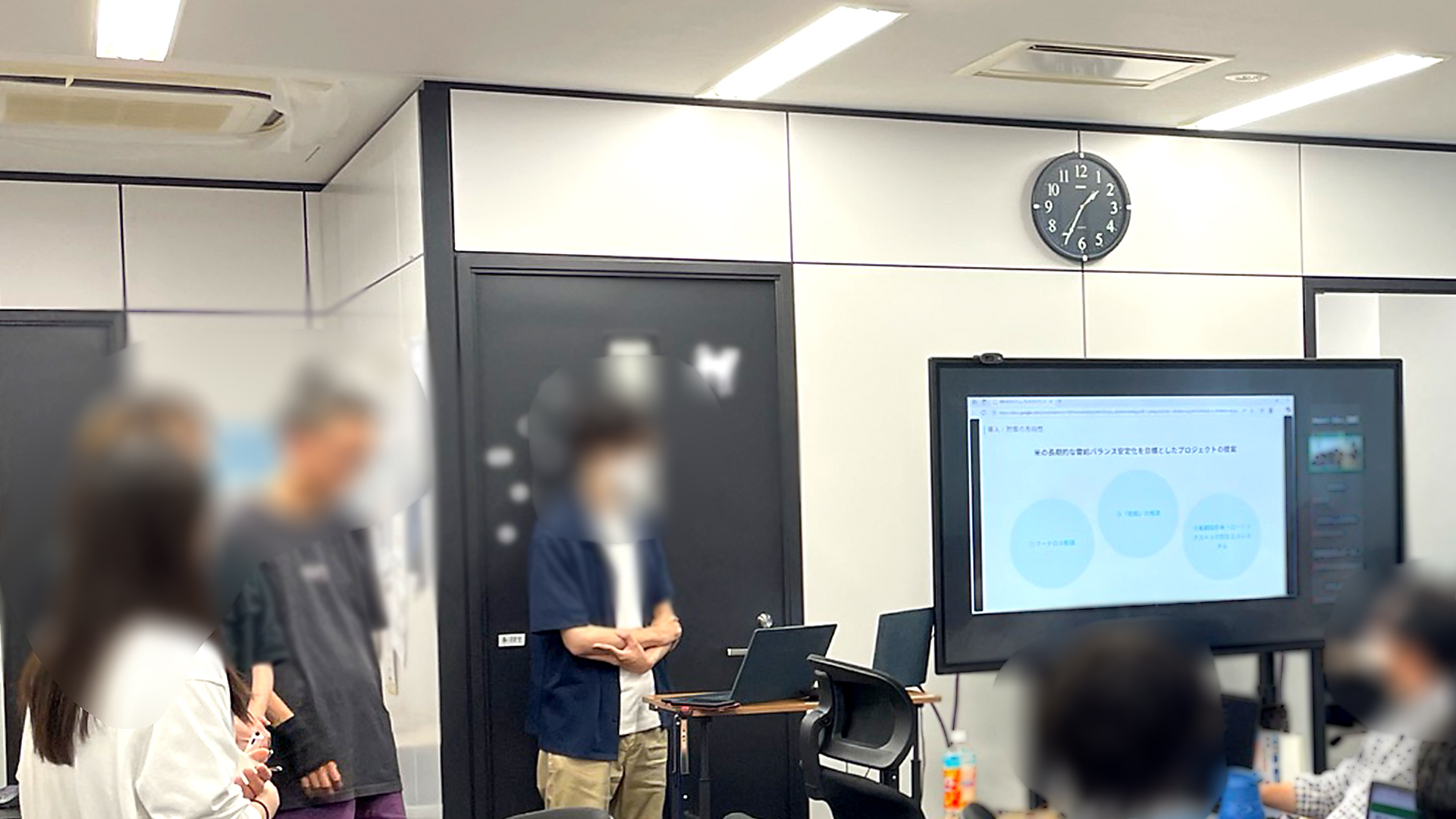
将来、ITエンジニアとしてキャリアを形成するには、クライアントや他部署の社員と合意形成を図る必要があり、プレゼンテーションスキルが不可欠です。そのため、Neuro Diveは擬似就労プロジェクトでも、成果発表会を通じて参加者の「伝える力」を磨いてほしいと願っています。
成果発表会は、実際のビジネスシーンを想定し、各チームがアイデアを売り込む形でおこないました。みな同じ目標を目指していましたが、各チームから出されたアイデアは視点がまったく異なるものでした。
三者三様のアプローチで各チームが舌戦!
各チームは次のようなタイトルと内容で、プレゼンテーションを繰り広げました。
| チーム | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| Aチーム | 「令和の米騒動」の分析と今後の対応 | 赤字が常態化している米農家の現状や、生産者と消費者の間にある価格認識のギャップに着目。 「米(マイ)レージプログラム」や「電気とお米の二毛作」など、生産と消費の双方を促すアクションプランを打ち出す |
| Bチーム | コメの消費を活性化させるために | 生産費の削減に焦点を当て、水門管理自動化システムや農薬散布ドローンの普及による稲作の効率化を提案。 IT技術を活用した「スマートライスセンター」の普及促進にも言及 |
| Cチーム | 米価安定化戦略 | 需給バランスの乱れと米価格上昇の関連性を指摘。 「フードロス削減」「乾飯(ほしいい)の推進」「ローリングストック防災エコシステム」という3つのアイディアを提案 |
「つくって終わり」にしない!評価&振り返り
擬似就労プロジェクトの真のゴールは、成果報告書の作成ではありません。継続的なスキルアップに向けて、学びを次に活かすプロセスが重要です。評価と振り返りを通じて、成功点の可視化と改善点の整理を行いました。
振り返りで得た「気づき」が成長のカギ
振り返りの時間を設け、KPT法を活用しながら「よかった点」「改善点」「今後に活かせること」を整理しました。
Aチームからは、「報連相の力とスケジュール管理能力が向上した」「生成AIの活用など新しいことに挑戦できた」など、スキル向上を実感する声が多く上がりました。
Bチームは、「自分の考えを表明できたが、アサーティブ・コミュニケーションを実践できない場面があった」と振り返り、自己発信とメンバーへの配慮を両立することの難しさを再認識したようです。
また、事前にスケジュール管理ツールの選定・導入を進めていたというCチームは、「スケジュールを管理しながら効率的にタスクを割り振ることで、チームの成果を最大化できた」とチーム運営に自信を深めた様子でした。
※アサーティブ・コミュニケーション:相手を尊重しながら自分の意見を伝えるコミュニケーション方法のこと
実践的な学びの場を提供するために
今回の擬似就労プロジェクトでは、データ分析や機械学習など「Neuro Dive」で学んだ先端ITスキルとともに、柔軟なクリエイティブシンキングの発現がみられました。空理空論に終わらず、現状に即したアイデアが提案された点は素晴らしかったです。
Neuro Diveでは、今後も実践的な学びの場を重視し、疑似就労プロジェクトを定期的に開催していく予定です。Neuro Diveに少しでも興味をもたれた方、サービスの詳細が知りたいという方は、定期開催しているWEB説明会へお気軽にご参加ください!
先端ITスキル向上を目指すあなたへ。
就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身に着け活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!
まずは資料請求から資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。
希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込む
